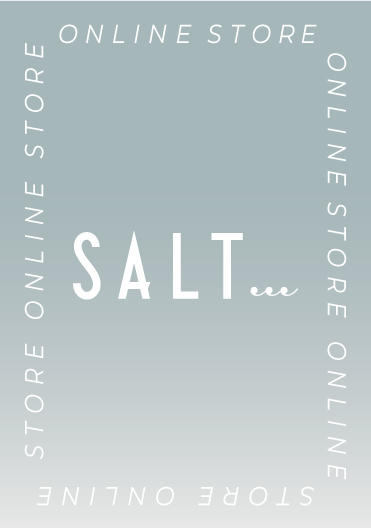#ビーチライフ

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/29_サマラ・クリブ
- 2026.03.02
海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile
Samara Cribb サマラ・クリブ
ゴールドコーストを拠点に活動するサーファー/クリエイター。海とともに育ち、マーケティング、フリーランス、スーパーヨットでの仕事を経て、あらためて“創ること”を軸に据えた。現在は、自身のクリエイティブな世界をさらに広げている。
あなたのことについて教えて
生まれ育ちは、バイロンベイの少し南にあるエバンズヘッドという小さな海沿いの町。のんびりとしたスローな空気が流れる、静かな田舎町。三姉妹の末っ子で、男の子がいなかったから、父にとって私たちは「サーフィンをさせるしかない存在」だったんじゃないかな(笑)。
毎週末のようにサーフィンの大会へ連れて行かれ、気づけば自然とサーフィン中心の生活ができあがっていた。まだ幼くて深く考えることもなく、ただ遊びの延長のような感覚でやっていたのを覚えている。三姉妹みんな一度はサーフィンをしていたけれど、続けたのは私だけ。父にとっては、きっと最後の希望だったんじゃないかな。今でも会うたびに「まだサーフィン続けてるのか?」って聞かれる。
子どもの頃は自転車で海へ向かい、毎日暗くなるまでサーフィンしてた。町はとても小さく、誰もが顔見知りで、道を歩けば何人もの人に声をかけられる環境。どこへ行っても誰かが見守ってくれているような安心感があった。その空気が大好きだった。
高校を卒業して20代に入る頃、少し物足りなさを感じるようになり、「もっとエネルギーがあって、刺激のある場所へ行きたい」と思い、ゴールドコーストへ引っ越したの。そして、いまはここが拠点。
大学を卒業してから、マーケティングやクリエイティブ、コンテンツ制作の分野で仕事している。大学では幅広く学べそうなビジネスを専攻し、自然な流れでマーケティングの道へ進んだ。19歳のとき、地元のスキンクリニックでSNSやコンテンツ制作を任せてもらうチャンスをもらった。当時は完全にゼロからのスタートで、ハイパーリンクの意味すら分からなかった。でもオーナーが一からすべて教えてくれて、その経験が今の土台になっている。20歳のとき、「自分でもできるかもしれない」と思ってフリーランスとして独立。周囲から「それは仕事にならない」と言われながらも少しずつクライアントが増え、気づけばフルタイムのような働き方になっていた。だけど22歳のとき、パソコンに向かい続ける生活に物足りなさを感じ始めて。もっとリアルなつながりや新しい刺激が欲しくなり、思い切ってマーケティングの世界を離れて、スーパーヨットの仕事へ飛び込んだ。そこで気づいたのは、「創ること」は自分にとって欠かせないものだということ。忙しさの中でクリエイティブな時間がなくなると、心のどこかが少しずつ削られていく感覚があった。いまはデザインをしたり、新しいアイデアを形にしたりする日々に戻り、心から満たされている。
サーフィンを始めたきっかけ
サーフィンを始めたのは、地元のエバンズヘッド。正直に言うと、サーフィンをしなかったら他にやることがあまりなかった、というのも理由のひとつ。父はいつも海に連れて行ってくれて、彼の友人たちもみんな私を知っていて、「また明日も海でね!」って声をかけてくれる。そんな環境の中で、自然とサーフィンが当たり前になっていた。そこから、地元や近くの大会に出るようになった。女の子同士でサーフィンをする感覚は、ゴールドコーストに来てから初めて知った。それまでは男の子たちと一緒に大会に出たり、一人で海に入ったり、父とサーフィンすることがほとんどだったから。ゴールドコーストはまったく雰囲気が違う。女の子のサーファーが自然に主役になれる場所、そんな印象。メインはロングボードで最近はミッドレングスにも挑戦している。少し前にインドネシアへ行ったときも、ミッドレングスだけを持っていった。
これまでいろいろな場所で波に乗ってきたし、これから行きたい場所もたくさんあるけれど、世界で一番好きなのは、クーランガッタのレインボーベイ。家から5分の場所に、世界で一番好きなブレイクがあるというのは本当に幸せなことだと思う。オーストラリア中を旅しながらサーフィンもしたし、西オーストラリアの海もとても美しかった。でも、ロングボーダーとして選ぶなら、やっぱりレインボーベイ。透き通った水、海へ向かう道から見えるスナッパーロックスからキラまでの景色。サンライズやサンセットの時間、海がやわらかな色に溶けていく瞬間。胸がきゅっとなるような、現実とは思えない景色。
もう一つ特別なのは、ロンボク島にあるエカスという小さなブレイク。次に行ってみたいのはモロッコとコスタリカ。


ゴールドコーストでの暮らし
小さな町で育った私にとって、大都市のシティライフはどこかしっくりこなかった。今でも自分の中には、あの小さな町の空気がちゃんと残っている気がする。少しストレスを感じた日は、ただ静かにビーチに座っていたくなる。地元を離れたばかりの頃は、今までにない忙しさや刺激を求めていた。でも時間が経つにつれて、本当の落ち着きや幸せは、静かな海辺で過ごす時間の中にあるんだと気づいた。ゴールドコーストのいいところは、その両方があること。仕事のチャンスや新しい出会いがある一方で、ひとりでビーチに座ってコーヒーを飲みながらぼーっとできる静けさもある。そのバランスがちょうどいい。
ここに住んでいる人たちは、「働くために生きている」というより、「ちゃんと暮らすためにここにいる」という感じがする。ブリスベンやシドニーへ行くと、都会のエネルギーに圧倒されることもあるし、人生が仕事中心に回っているように見えることもある。でもここは、平日の朝でも海沿いを歩けば、ランニングしている人、トレーニングしている人、ビーチでのんびりしている人がいる。その景色を見るだけで、自分の神経もすっと整っていく。自然と深呼吸したくなるような場所。

海、自然との関係
サーフィンは、私にとってある意味“瞑想”みたいなもの。正直、静かに座ってする瞑想はあまり得意じゃない。頭の中はいつも忙しいし、「もっと上手くなりたい」とかいろいろ考えてしまう。でも海に入ると、不思議と余計なことが消えていく。2時間くらい海に浮かんで、誰とも話さず、ただ波を待つ時間。それは自分と海だけの時間。すごく静かで、でもちゃんと生きている感じがする。
海に入って後悔したことは一度もない。たとえ思うように波に乗れなかった日でも、海から上がる頃には必ず「入ってよかった」と思えている。海は、ほかではなかなか得られない深い静けさをくれる。同時に、海の力を絶対に侮らないようにしている。特に海のそばで育っていない人や初心者の人は、そのパワーを甘く見てしまうこともあると思う。大きな波、カレント、潮の流れ、風。完全に自然のエレメントの中にいるということ。
「今日はコントロールできてる」って思った瞬間に、まるで海が「考え直しなさい」と言わんばかりに、一瞬で打ちのめされることもある。だから自分は、海の“上”に立っている存在ではなく、海の“下”にいる存在。海に入るたびに、謙虚さを思い出させてもらっている。
人生に欠かせない3つのもの
一つ目は、ビーチや海のそばにいること。どんなに条件がよくても、そこに海がないなら選ばないと思う。それくらい、海は人生の前提。
二つ目は、体を動かせること。スーパーヨットで働いていた頃、自分だけの静かな時間がほとんどなく、思うように運動もできなかった。そのとき初めて、体を動かすことがどれだけ自分の心とつながっているかを実感した。動けないことは、想像以上にメンタルにも影響していた。
三つ目は、コーヒー。これはもう、シンプルに欠かせない存在。朝の一杯で、気持ちがちゃんと整う。

今後の夢と目標
まだ若くて、大きな責任がそこまでない今のうちに、できることは全部やってみたい。その一つが、パートナーと海外に住むこと。同時に、仕事のスタイルもきちんと整えたい。自分にとって譲れないものを大切にしながら、落ち着きもあって、でも旅も続けられる。そんなバランスを見つけたいと思っている。
これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス
一番伝えたいのは、自分のエゴに邪魔されずに人に話しかけること。たった5分の会話でも、少し素直になって「実はこれ、よく分からない」とか「教えてほしい」と言えるだけで、何かが動き出すことがある。オープンな心で、オープンな姿勢で質問すること。この世の中のすべてを知っている必要なんてないし、そんな人はいない。でも、たった5分の会話が自分の人生を変えることもあるし、もしかしたら相手の人生を変えることだってあるかもしれない。
私自身、新しいことを始めるときは、すでにやっている人に「どう思う?」と素直に聞いてきた。それだけ。
サーフィンも同じで、「準備が完璧に整う日」なんてきっと来ない。だから飛び込むしかない。ずっと岸で座って、完璧な瞬間を待っていても、そんな日はたぶん来ないから。

text:Miki Takatori
20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram
TAG #Ocean People#Samara Cribb#サマラ・クリブ#ビーチライフ#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/28_アニカ・マッコマーク
- 2026.02.16
海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile
Anika McCormack アニカ・マッコマーク
オーストラリア・ヌーサを拠点に活動するアーティスト。サーフィンと旅を通して出合う風景や色、人とのつながりを、どこか懐かしさを感じるレトロな感性で作品に落とし込んでいる。
あなたのことについて教えて
生まれはオーストラリアのメルボルン。5歳の頃に北にあるサンシャインコースト・ヌーサへ引っ越し、今ではここが私のホーム。昨年12月に仕事を辞め、現在はフルタイムでアーティストとして生計を立てることを目指し、日々模索している。
実は数日前に、メキシコへのサーフトリップから帰ってきたばかり。アートのインスピレーションも数えきれないほど受けた。旅はメキシコのサラディタ(La Saladita)から始まり、メキシコシティまで続いた。滞在中はスウェルが少なく小波が続いていたけど、私たちが帰国した途端に良い波が入り始めたと聞いて、また必ず戻りたいと思っている。
サーフィンを始めたのは2年前から。子どもの頃からヌーサに住んでいて、海はいつも身近な存在だったのに、なかなか始めるきっかけがなかった。今のパートナーと出会ったことをきっかけに、一気にのめり込んだ。それからはほぼ毎日サーフィンをするようになり、ヌーサ国立公園に入るのが日常になった。今はローカルシェイパー、Thomas Surfboardの9’4"に乗っていて、新しいボードももうすぐ届く予定。すごく楽しみにしている。
普段は朝4時に起きて、日の出前から海に。帰ってからはアート制作に取りかかり、波が良ければ夕方にもう一度サーフィンをしに行く。とてもシンプルだけど、この生活が本当に好きで、ずっと思い描いていたライフスタイルそのもの。
パートナーと出会ったのは高校生のとき。一緒にサーフィンを始めてから、同じ趣味を持つことで関係がぐっと深まったと感じている。今では話すことも、やることも、ほとんどがサーフィン。彼は撮影にもすごく力を入れていて、それが私のサーフィンの上達にもつながっている。お互いにサーフィンしているところを撮り合うのが最近の楽しみで、サーフィンを通して一緒に成長していけるのが素敵だなと思っている。
ホーム、ヌーサの魅力
ヌーサは、私にとってとても特別な場所。海沿いに広がる小さなサーフタウンで、どこを切り取っても絵になる街だと思う。オーストラリアの他の地域と比べても人々は穏やかで、訪れる人の多くがこの街を好きになる。
サーフシーンもすごく面白くて、私が暮らしているエリアはロングボードにぴったりの波が立つ場所。ヌーサ発祥のサーフボードやサーフアパレル、ブランドも多くて、スタイルのあるサーファーが集まっている。海の中では、優雅にクロスステップやハングファイブを決めるサーファーが多く、海に入るたびに「あんな風に乗れたらいいな」とインスパイアされてる。それが、自然と毎日海に向かいたくなる理由のひとつになっているかも。
プロのロングボードの大会や、ヌーサ・ロングボード・フェスティバルなど、1年を通して色々なイベントがあるのもこの街の魅力。毎年それを観るのが楽しみで、そのたびにロングボードカルチャーの奥深さを感じている。中でもお気に入りのサーファーは、バイロンベイ出身のJosie Prendergast。あのスタイルと、ボードの上での華麗な佇まいは、やっぱり彼女にしか出せないものだと思う。


アートを始めたきっかけ
幼い頃から、アートは常に身近な存在だった。サーフィンを始めてからは特に、サーフトリップで訪れる土地や、海から見える景色や色、人とのつながりが、自然と自分のアートに反映されるようになったと感じている。
最近はレトロなテイストに惹かれており、集中している時は1日で描き上げることもあれば、1週間近くかかることもある。アートはあくまでも“本当に好き”という気持ちの延長線上にあるもの。ビジネスにしたい、有名になりたいという願望はなく、自分にプレッシャーをかけない範囲で続けている。だからこそ長く続き、本当に描きたいものを描けていると思う。夢は、いつか自分の作品で個展を開くこと。



海、自然との関係
海に入っていると、いい意味で思考が停止する。次に来る波や、周囲や海の状況のことしか考えていないから、日常生活での悩みや不安から解放される。たとえ波が良くなくてもパドルアウトするだけで気分が良くなるし、サーフィンは、マインドにもボディにも良い影響しかないと思う。
これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス
私が伝えられるとしたら、何事にもポジティブでいること。考え方ひとつで違う方向へ進んでしまうこともある。前向きに、起こることすべてを受け入れる気持ちでいると、最終的には自分にとって必要な形に、きちんと収まっていくはずだから。

text:Miki Takatori
20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram
TAG #Anika McCormack#Ocean People#アニカ・マッコマーク#ヌーサ#ビーチライフ#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/27_ダナ・ハマン
- 2026.02.02
海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile
Dana Hamann ダナ・ハマン
カリフォルニア・サンディエゴ出身。18歳でハワイへ移住し、現在はロンボクとハワイを行き来しながら、サーフィンとセルフアウェアネスを軸にしたリトリートを主催している。
あなたのことについて教えて
生まれ育ちは、カリフォルニアのサンディエゴ。高校を卒業した18歳のときにハワイ・オアフ島へ移住し、現在はインドネシアのロンボク島とハワイを行き来する生活を送っている。ここ3年以上は、サーフリトリートをフルタイムで主催してきた。でも今は、人生やビジネスにおける次のステージを模索する、ひとつの移行期間にいると感じている。
私が開催してきたリトリートは、「サーフィン × セルフアウェアネス(自己認識)」をテーマにしたもの。サーフィンの技術向上やマインドセットに深くフォーカスしながら、自己探求や、まだアクセスできていない自分自身の一部に触れていく時間も大切にしている。ラインナップを共有し、海や自然の中で過ごす時間を通して、参加者同士が正直に心を開ける場所、コミュニティをつくりたいという想いから始めた。参加者は皆、「学び、成長したい」という意欲を持ち、さらに旅という非日常の中で、目の前の体験に集中できる環境にいる。深い対話が生まれるための、完璧な条件がそこにはあった。
オーバーツーリズム、発展が著しいインドネシアのシーンとサーフィンとの葛藤
2025年は、インドネシアやサーフィン業界の変化も重なり、かなり自分の殻にこもっていたと思う。バリと同じように、ロンボクを訪れる人の数が一気に増え、そこに集まる人たちの層が変わってきた。その変化を受け入れるのが、正直難しかった。
昔みたいにローカルフードを食べ、ホームステイに泊まる生粋のサーファーたちではなく、今は温かいお湯が出るお洒落なヴィラに泊まり、アボカドトーストを食べ、西洋的なライフスタイルをそのまま持ち込んでいる人が多い。それ自体が悪いことだとは思わないけれど、今のロンボクは、欧米人に向けてつくられた世界のように感じてしまった。
コロナ以降、サーフィン業界は大きく変わり、ここ数年は過去最高に盛り上がり、収益性も高い時代になった。でも個人的には、その変化に強い葛藤を感じてきた。
私は幼い頃からサーフィンと共に生きてきたから、コロナ後にサーフィンと深い関わりを持ってこなかった人たちが、利益だけを目的にこの業界へ参入してくる姿を見るのは、正直つらかった。もちろん、彼らを責めることはできない。それでも、サーフィンの文化や歴史、エチケット、リスペクト、レガシーを理解しないままビジネスをつくっていく姿を目にすることで、自分自身の情熱が少しずつ削がれていくのを感じていた。
私は、サーフィンが生まれた理由や、文化を超えて大切に受け継がれてきた背景を守りたいと思っている。だから今、この業界の中で「自分はどんな形で存在したいのか」を改めて考えている。SNS的なサーフィンではなく、もっと本質的な部分から人を教育し、インスパイアできる関わり方を探している。


サーフィンを始めたきっかけと、お気に入りのサーフスポット
初めて波に乗ったのは2歳のとき。父親がサーファーで、ボードの前に一緒に乗せてもらったのがサーフィンとの出合いだった。5歳の頃から自分の波にプッシュしてもらうようになったけれど、子どもの頃はサーフィンはずっと「遊び」の一部。本気で向き合い始めたのは12歳くらいから。いとこたちと海で遊ぶときもサーフィンが当たり前で、そこからサーフィンは、私の生活の大部分を占める存在になっていった。
お気に入りのサーフスポットは、ロンボクのタンジュアンビーチ。世界中のたくさんの波に乗ってきたけれど、間違いなくタンジュアンが世界で一番好きな波。次に行きたい場所はモルディブ。最近出会った友人から、モルディブはサーフィンだけでなく、充実したマリーンアクティビティも楽しめると聞いて、近いうちに必ず行こうと思っている。
海、自然との関係
自然の中に身を置くことは、人生で感じてきた中で一番の「自由」を与えてくれる。海で過ごす時間は、ただ気持ちいいというだけでなく、自分の内側や魂の奥まで染み渡るような感覚。体がふっと軽くなり、今この瞬間に意識が向き、心が穏やかになって、どんな状況でも「生きていること」そのものに感謝できるようになる。
たとえ人生で何が起きていようと、どんな課題に直面していようと、体調を崩していても、健康や仕事、家族、ビジネスのことで悩んでいても、海にいるととにかく解放されて自由になれる。その経験を通して、普段の社会の中では見過ごされがちな、シンプルでささやかなことの尊さに気づかせてもらった。水(海)という自然の要素と、これほど健やかで深いつながりを持てていることに、ただただ感謝の気持ちでいっぱいになる。


これからの目標
もうすぐ30歳になあるんだけど、気づけばサーフィン歴は25年以上になる。去年開催したあるリトリートの最中、ふと、これまでサーフィンはずっと“誰かのため”にやってきたのだと感じた。10代から20代前半までは高校のサーフチームに所属し、もともとアスリート気質で負けず嫌いな性格もあって、大会で結果を出すためにスキル向上に集中してきた。それって今振り返ると、外からの評価や承認を求めていた部分が大きかったと思う。
そして20代前半から後半にかけては、ビジネスとしてレッスンやコーチング、サーフリトリートを開催したりして、サーフィンは常に“誰かと共有するもの”だった。30代に入るこれからは、サーフィンを“自分のためのもの”として大切にしたいと、強く思うようになった。もちろん、海の中で人をサポートする仕事への情熱は今でも変わらない。でも久しぶりに、誰かのためではなく、まずは“自分のためにサーフィンをする”ことを優先したいと思っている。
仕事の面では、ここ数年リトリートを開催してきた経験を通して、新しい形のサービスを始めることにワクワクしている。これまで、ガイドやサポーター、ときにはカウンセラーやセラピストのような役割で、人の旅に寄り添ってきた。今はその経験を活かして、本当の意味で人の役に立てる、持続可能なプログラムをつくりたいと考えている。まだ具体的な形は見えていないけれど、必ず形になる気がしている。

あなたの生活に欠かせない3つのもの
海、なんでも話せる友達、そして深いつながりを持てるコミュニティ。
これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス
すごくありきたりかもしれないけれど、自分を信じること。私は16歳のときにサーフィンを人生の道として選んだ。そのときは誰も「できる」と信じてくれなかったけれど、何があっても、自分が本当に信じていることや、心から望んでいることに正直でいれば、思い描いていた通りの形でなくても、最終的にはちゃんと辿り着けると思っている。

text:Miki Takatori
20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram
TAG #Dana Hamann#Ocean People#ダナ・ハマン#ビーチライフ#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/26_ナオミ・フォルタ
- 2026.01.09
海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile
Naomi Folta ナオミ・フォルタ
アメリカ東海岸出身。沖縄とボストンにルーツを持ち、サーフィンとスケートを軸に世界を旅する、「GRLSWIRL」のライダー兼クリエイター。多文化環境で育った経験を強みに、海とコミュニティを通じて女性が自分らしく挑戦できるスペースを広げる活動を続けている。
あなたのことについて教えて
アメリカ東海岸・北バージニア州の出身で、母は沖縄、父はボストン出身。小さい頃から沖縄空手をはじめて、チアリーディングや体操、陸上など、両親が勧めてくれたスポーツをとにかくいろいろ経験してきた。毎年夏になると沖縄に行って、母が通っていた地元の小学校・中学校・高校に1ヶ月ほど通いながら、父の空手道場のコミュニティの中で過ごしていた。いつも沖縄の文化がすぐそばにあって、すごくアクティブな環境で育ったと思う。
スケートボードとサーフィンを始めたのは20代に入ってから。大学では機械工学を専攻して、卒業後は1年間エンジニアとして働いていた。でも、「やっぱりスケートもサーフィンも、好きなときにできる生活がしたい!」と思うようになって、仕事を変えた。それが、私の人生を大きく変えるきっかけになった。
今はGRLSWIRLという女性だけのスケートチームのライダー(8〜9人いるメンバーのうちのひとり)として活動しながら、グラフィックデザイナー、イラストレーター、モデル、そしてSNS関連のフリーランスも手掛けている。子どもの頃からいろいろなことに挑戦してきたから、複数のことを同時にやるのはわりと慣れている。
サーフィンを始めたきっかけ
一人旅やバックパッキングが大好きで、大学卒業後に東南アジアを約1年かけて旅した。旅の途中でフィリピンに辿り着いて、サーフィンもダイビングもハイキングもできるし、何をしようか考えていたとき、ホステルで出会った人に「これからサーフタウンに行くけど、一緒に行かない?」って声をかけてもらった。そして向かったのが、サンフアン・ラウニオン(San Juan La Union)。そこで初めてサーフレッスンを受けて、多くの人がそうなるように、あっという間にハマってしまった。「ちゃんと乗れるようになるまで、この町を離れない」って決めて、気づいたら2ヶ月くらい滞在していた。そこが、私が本当にサーフィンを覚えた場所。
今はロングもショートもどちらも好きで、憧れのサーファーは、ジョージー・プレンダーガスト。滞在していたサーフタウンには女性ロングボーダーがすごく多くて、彼女たちの華麗でスタイリッシュなライディングを見るたびに、もっと上手くなって「クロスステップして、ノーズまで行きたい」って思うようになった。
お気に入りのスポットは、太平洋側のメキシコ。よく行くエリアで、大好きな波がたくさんある。次に行きたい場所は、フィリピンのシャルガオとモロッコ。


日本とアメリカの両方で育った経験、それが今の自分にどんな影響を与えている
沖縄は西洋文化の影響も強く受けていて、そこが少し特別な感じ。一番違いを感じたのは“責任感”の部分だった。日本の学校では、自分たちで教室を掃除したり、給食を取りに行って配膳したり、「自分たちでやる」ことが当たり前。それがすごく新鮮だった。アメリカの学校では、そういう経験がなかったから。
アメリカの学校は、また違う意味で自由というか……。女の子でもサッカーをしたり、大きな声で笑ったり、ちょっとアグレッシブでも全然OK。でも日本の学校に行ったとき、男の子たちとサッカーをしたくても、一緒にやりたい女の子が全然いなくて、「え? みんなどこ?」って思ったのを覚えている(笑)。そういう文化や空気感の違いを見るのが、すごく面白かった。
沖縄では、“アメリカの私”と“日本の文化を大切にする私”を、自然と使い分けていた。当時はまだSNSが普及していなかった2000年代で、私や兄、他のハーフの友達は、周りの子たちから「誰?」「何してるの?」「アメリカってどんな感じ?」と、すごく興味を持たれる存在だった。
そうした経験から、自然と適応力が身についたと思う。どんな場所でも自分を調整して馴染めるし、文化や背景の違う人の気持ちも理解できるようになった。毎年同じ友達に会っていても、学校に通うのは1ヶ月だけだから、いつも“新しい転校生”みたいな感覚。それが、人の気持ちに寄り添う力や共感力につながったと思う。責任感も強くなったし、自分でいろいろできるようになったことで自信もついた。その感覚は旅をするときにもすごく役立っていて、どこに行っても自分で立て直せるし、環境にもすぐ順応できる。女性としても、「女の子だって、自分の世界を広げていい」「挑戦していい」という感覚が、自然と身についた気がする。
GRLSWIRLでの活動
GRLSWIRLのチームライダーとして声をかけてもらったのは、2年近く前。カリフォルニアに引っ越したのが2022年8月で、そのときは仕事もなくて、手元のお金も1,000ドルくらい。叔父さんの家にお世話になっていた。それでも、「サーフィンとスケートを思いきりやって、たくさんの女性たちとスポーツを楽しむ生活がしたい」という気持ちが強かった。GRLSWIRLの本拠地がヴェニスだと知ったとき、「これだ」って思った。初めて参加したスケートのミートアップは、本当に魔法みたいな時間だった。50人以上のガールズたちが集まって、ヴェニスのスケートパークから桟橋まで、みんなでスケートしていく。その光景は、まさに思い描いていたカリフォルニアのシーンだった。周りは素敵な女性ばかりで、スケートして、サンセットを見て、笑って。ただ一緒に滑っているだけなのに、心の底から満たされる時間だった。その瞬間から、「この感覚をずっと感じていたい」「この人たちと一緒にいたい」と思って、すべてのイベントに参加して、ボランティアも続けた。そうして活動しているうちに、いつも積極的に参加してスケートしている姿を見てくれていたメンバーから、チームに入らないかと声をかけてもらったの。今はチームの一員として、同じような境遇のガールズたちを支えながら、コミュニティを広げている。


海、自然との関係を言葉で表すなら?
子どもの頃から沖縄でたくさんの時間を過ごしてきたから、海は私にとってすごく身近で、安心できる場所。家族や友達がいつも海に連れて行ってくれて、シュノーケリングをしたり、ボートに乗ったり、泳いだりしていた。だから自然とのつながりは、ずっと強く感じている。自然は、自分に戻れる場所であり、好奇心を思い出させてくれる場所。海にいると「帰ってきた」っていう安心感があって、サーフィンをしているときは、力強さとしなやかさ、その両方を自分の中に感じられる。
これからの目標
ロサンゼルスのNPO「Los Courage Camps」でボランティアとして活動し、さまざまなバックグラウンドを持つ子どもたちに、無料でサーフィンレッスンをしている。サーフィンって、実はハードルの高いスポーツ。サーフボードやウェットスーツが必要だったり、海に行くにはクルマが必要だったり、LAだと駐車場代もかかったりして、それだけで大きな負担になる。私たちは、そうしたハードルをすべて取り払って、ボードもウェットもレッスンもすべて無料で提供している。人生で初めて海に入る子や、その年に初めて海を見る子もいる。私の夢は、サーフィンを通して、彼らが一緒にサーフトリップに行ける友達に出会ったり、何でもシェアできるサーフコミュニティを見つけてくれること。
もうひとつの大きな夢は、沖縄でローンチしたGRLSWIRLをサポートすること。立ち上がったばかりだけど、その広がりを手伝いながら、レベルや見た目に関係なく、誰でもスケートを楽しめるコミュニティを育てていきたい。


あなたの生活に欠かせない3つのもの
コラージュジャーナル、サーフボードとスケートボード、それからピクルス。
これから何か新しいことに挑戦したい人へのアドバイス
大切なのは、「こうなってほしい」という期待を手放すこと。新しいことを学ぶときや、新しい場所に行くとき、何かを始めるときは、その結果よりもプロセスにちゃんと向き合って、今この瞬間を感じることが大切だと思う。期待で自分を縛ってしまうと、その時点で可能性は狭まってしまう。だからこそ、目の前で起きるいろいろな経験をそのまま受け止めて、プロセスを楽しむこと。それが一番大事だと思っている。

text:Miki Takatori
20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram
TAG #GRLSWIRL#Naomi Folta#Ocean People#ナオミ・フォルタ#ビーチライフ#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/25_エマ・ダンゾ
- 2025.12.15
海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile
Emma Danzo エマ・ダンゾ
アメリカ出身、現在はバイロンベイを拠点に様々なブランドのマーケティングを行うクリエイティブディレクター。海と旅から得たインスピレーションを軸に、ストーリーのあるビジュアルとブランド体験を創出している。
あなたのことについて教えて
生まれ育ちは、ニューヨークからクルマで45分ほどのニュージャージーにある小さな街。父がイタリア出身だったこともあり、幼い頃から家族みんなで料理をしたり、家族同士のつながりを大切にする環境で育った。旅行にもよく出かけ、毎年少なくとも一度はイタリアに帰って家族に会い、ヨーロッパ各地も旅していた。アメリカに住みながらも、アメリカとイタリア、両方の文化の中で育ってきたように感じている。
18歳のときにカリフォルニアへ移り、サンタバーバラの大学でコミュニケーションを専攻した。在学中にパンデミックが起こり、友人がサーフィンをしていたこともあって私もサーフィンを始めた。それが人生を大きく変えるきっかけになったの。
大学で学んでいたマーケティングと、夢中になっていたサーフィンを結びつけたいと思うようになり、サーフィン業界でキャリアを築きたいと感じ始めた。パンデミックを通して働き方が大きく変わり、オンラインで働くことや、ブランドがSNSを通じて人々とつながる時代に移行していくのを肌で感じていたわ。
私はデザインも写真も文章を書くことも好きだったから、SNSはそれらをすべて結びつけられる理想的な場所だった。最初はサンタバーバラにあるサステイナブルな日焼け止めブランドでフリーランスとして働き始め、その会社を通じて多くのパートナーシップやつながりが生まれ、ブランドを大きく成長させることができた。次第に、同じような仕事を依頼したいというブランドが私のもとに来るようになり、気づけば小さなサステイナブル系サーフブランドや非営利団体を中心に、自分の専門領域のポジションが自然とできあがっていたの。特に営業や宣伝をしなくても仕事が途切れず、ビジネスが自然と形になっていき、そのおかげでフルタイムで旅をしながら働く生活が実現した。
大学卒業後、家にあったものをすべて手放し、バリ行きの飛行機に乗って数ヶ月過ごした。その後オーストラリアに移住し、気づけばもう2年。バイロンベイを拠点に、バリに戻ったり、アメリカに帰ったり、ヨーロッパへ行ったり、世界中のサーフスポットをめぐりながら、仕事でつながったブランドの人たちに実際に会い、思い描いていた日々を過ごしている。
オーストラリアへの移住
幸運なことに約半年前、世界的に有名なシェフから声をかけてもらったの。ミシュランの星を持つシェフで、彼が自分の会社2社のSNSとマーケティングマネージャーとして私を雇ってくれた。その縁でビザのスポンサーにもなってくれ、この半年は私にとって大きな転機だった。
フルタイムで旅をしながらビジネスを回す生活は素晴らしい経験だったけれど、正直疲れることも多かった。多くを学び、たくさんの出会いがあり、本当に感謝しているし、やりたかったことは全部やれたと思う。これからはもう少し “普通の生活”、つまりルーティンがあって、家があって、友だちやコミュニティがあって——そんな環境の中で、オーストラリアで腰を落ち着けてキャリアを積んでいく時期に入ったと感じている。


サーフィンを始めたきっかけ
初めてサーフィンをしたのは5年前の2020年。当時、親友の友人が、子どもの頃から海に入っているような上手なサーファーの男の子と付き合い始め、その彼が一緒にサーフィンしようと誘ってくれた。その日の海はまったく怖くないコンディションで、カリフォルニアの暖かく心地いい日差しが広がる、とても気持ちいい日だった。
波に合わせてパドルして、立ち上がった瞬間の感覚を今でも覚えている。本能的に体が動いたようにスッと立てて、海との“つながり”というか、「あ、知っている感覚だ」と思うような不思議な懐かしさが一気にこみ上げてきた。海と完全につながったような感覚だった。
好きなサーファーは Torren Martyn(トレン・マーティン)。彼のエフォートレスなスタイルが本当に好き。私はミッドレングスからサーフィンを始めたので、少し大きめのボードで、しかもサイズのある波でも軽々とターンしていく姿に強く影響を受けたわ。普段はシングルフィンのミッドレングス、ツインフィン、そしてロングボードにもよく乗っている。
お気に入りのサーフスポットと次に行きたい場所
バイロンベイの “The Pass”。多くの人に愛されるスポットだけれど、私にとっては本当に“ホーム”のような場所。パドルアウトするたび、みんなニコニコしていて、混雑にイライラしている人もたまにいるけれど、顔見知りが多いからコミュニティの温かさをいつも感じる。波はいつも最高で、ほとんどどんな日でもサーフィンできるし、水は透き通っていてイルカもいて、景色も本当に美しい。ここに来ると必ず幸せな気持ちになる。
次に行きたいのは日本! バイロンベイにも日本人の友達がいて、彼らの育った場所を見に行く旅をしたい気持ちがどんどん強くなっている。


何か新しいことを始めたい人へのアドバイス
怖さや不安、「できないかもしれない」という気持ちに引っ張られるのは普通のこと。多くの人が「それは無理」「大変すぎる」と言うかもしれない。だけど、自分の情熱に従うとき、宇宙が後押ししてくれるように物事が動き始める。自分を信じ、自分のビジョンを信じ続ければ、実現する方法は必ず見つかる。
面白いことに、目標に集中してまっすぐ向かっていると、現実が少しずつ形になっていく。無意識のうちにチャンスや出会いを引き寄せ、その“現実”を自分で創っていくことができるようになる。

text:Miki Takatori
20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram
TAG #Emma Danzo#Ocean People#エマ・ダンゾ#ビーチライフ#連載

- 【特集:Ocean People】海から始まるストーリー/24_パトリシア・ピサンマ
- 2025.10.21
海と繋がり、自分の中の好きや小さなときめき、そしていい波を追い求めてクリエイティブに生きる世界中の人々、“Ocean People”を紹介する連載企画。彼らの人生を変えた1本の波、旅先での偶然な出会い、ライフストーリーをお届けします。

Profile
Patricia Phithamma パトリシア・ピサンマ
ハワイ生まれサンディエゴ在住。機能性とデザインを兼ね備えたスイムウエアブランド「Tan Madonnas」を立ち上げ、海を愛するすべてのアクティブな女性たちに向けて発信している。
あなたのことについて教えて
生まれはハワイのオアフ島。6歳のときにアメリカ本土のワシントン州へ引っ越したけれど、それ以降も頻繁にハワイには戻っていた。父がサーファーだったこともあって、幼い頃から海で過ごす時間が大好き。いつか自分もあんなふうにサーフィンができたら──とずっと憧れていた。
高校を卒業した8年前、カリフォルニアのサンディエゴにへ移り住み、今もここを拠点に生活している。サンディエゴは、サーフィンとアメリカのカルチャーがバランスよく混ざり合う、とてもクールなサーフタウン。サーフィンを本格的に始めたのも、この街に引っ越してきてから。
お気に入りのサーフスポットは地元のラホヤ。特別に波がいいわけではないけれど、海に行けば必ず友達に会える。その“ホーム感”がたまらなく好き。
そして、世界で最もパーフェクトな波がある──インドネシアのメンタワイ諸島。あそこは本当に特別だと思う。
次に行きたい場所はモルディブ。楽しそうなライトの波がたくさんあるし、サーフィン以外にもできるアクティビティが充実してるから、近々行きたいと思っている。
ブランドを始めたきっかけ
スイムウエアブランド 「Tan Madonnas」を立ち上げたのは2022年。海の中でもしっかりホールドしてくれるビキニ、そしてアクティブウエアとしても着られるデザイン性のあるビキニをずっと探していたけれど、なかなか“これだ”と思えるものに出合えなかった。それに、サンディエゴ発のブランドって意外と少なくて、だったら、自分で作ってみよう! と思ったのがきっかけ。最初は試行錯誤の連続だったけど、今ではブランドの方向性も明確になり、どんなデザインを展開していきたいかもクリアになってきた。やっと軌道に乗ってきたなって感じている。
「Tan Madonnas」を着た女の子たちがサーフィンやスケートをしている写真を見ると、「本当に作ってよかった」と心から思う。これからの目標は、もっと多くの人に手に取ってもらうこと。そして、アクティブでクールなガールズたちが繋がれるコミュニティや、サーフトリップなども企画していきたいと思っている。


海、自然との関係を言葉で表すなら?
海のない生活は考えられない。仕事で行き詰まったとき、リフレッシュするためにパドルアウトして、思いがけずいい波に乗れた瞬間に、ムードが一気に変わったりする。サーフィンをしていなかったら行かなかったような場所にも行くようになったし、海以外では出会えないような面白い人たちにも出会えた。いい意味で、サーフィンは人生を変えてくれたと思う。
他のスポーツや趣味と違って、サーフィンには終わりがない。長く続けているからといって必ず上手くなるわけじゃないし、ひとつの技を習得するのに何年もかかることもある。それに気づいたとき、焦らず自分のペースで続けようと思えた。サーフィンは私の人生の一部だし、これからもずっと人生の基盤であり続けると思っている。
あなたの生活に欠かせない3つのものは?
ビーチサロン、サーフボード、そしてもうひとつはすごくランダムだけど——アイブロウペンシル!


何か新しいことを始めたい人へのアドバイス
何かを始めるときに、すべてが揃うまで待たなくてもいいと思う。まずは始めてみて、そこから試行錯誤を重ねればいい。完璧なタイミングなんてないと思う。
そして、ときにはプロの力を借りることも大切。ウェブサイトを作ってもらったり、デザイナーに相談したり。自分では気づけない視点を持っている人たちから、学べることって本当にたくさんあるから。

text:Miki Takatori
20代前半でサーフィンに出合い、オーストラリアに移住。世界中のサーフタウンを旅し現在はバリをベースに1日の大半を海で過ごしながら翻訳、ライター、クリエイターとして多岐にわたって活動中。Instagram
© SALT… Magazine All Rights Reserved.
© SALT… Magazine All Rights Reserved.